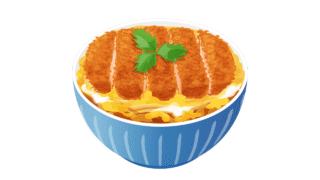「履歴書を何時間もかけて書いたのに、面接官はほとんど見てないんじゃないか?」
そう思ったことはありませんか。
正直に言うと──その通りです。
もちろん、最低限の確認(名前、学歴、資格、志望動機欄など)はします。ですが、私たち面接官が本当に重視しているのは、履歴書の中身そのものではありません。
面接官が履歴書をどう使っているのか
履歴書は「会話のきっかけ作り」にすぎません。
たとえば「アルバイト経験に家庭教師と書いてあるな。じゃあコミュニケーション力について聞いてみよう」──そんな程度です。
つまり履歴書は、料理でいえば“前菜”。
本番の料理(=面接の会話)を引き立てるための道具でしかありません。
書類よりも、その場の「空気」
では、面接官が何を見ているのか。
- 話の一貫性
- 質問に対する反応の速さや柔らかさ
- 表情や声のトーン
- 相手に伝えようとする姿勢
これらは履歴書からは絶対に分かりません。
たとえば、履歴書には「協調性があります」と書かれていても、実際に話してみて会話をかぶせたり、相手の言葉を遮ったりする人もいます。その瞬間に「あ、この人は協調性を履歴書に書いただけかもしれない」と伝わってしまうのです。
面接官の本音トーク:惜しいパターン
パターン1:履歴書を丸暗記している
面接官「アルバイトはどんな経験でしたか?」
学生「はい、私は居酒屋で2年間アルバイトをしており、そこでチームワークの大切さを学びました」
──履歴書と同じ文章が返ってくると、がっかりします。
会話が広がらないからです。
改善例:
「居酒屋で、常に忙しくて…でも、ピークタイムを乗り切るために店長が工夫していて、それを自分なりに真似しました」
こう答えるだけで「実体験のエピソード」になり、会話が深まります。
パターン2:立派なことを書きすぎる
履歴書に「社会貢献したい」と書いてあるのに、面接で「えっと…安定しているから選びました」と言ってしまうケース。
これは非常に多いです。
「履歴書に書いた理想」と「口から出る本音」がズレていると、一気に信頼が下がります。
改善例:
「正直、安定も魅力に感じました。ただ、実際に業界を調べていくうちに、社会にどう役立てるかという視点が自分にとって大きいと気づきました」
といったように、本音と建前をブリッジする答え方がベストです。
パターン3:エピソードが抽象的すぎる
履歴書に「リーダーシップを発揮」とだけ書いてあるケース。
実際に聞いてみると、「みんなをまとめました」と抽象的な説明で終わってしまう。
改善例:
「学園祭の準備で、途中で班のメンバーがやる気をなくしてしまったんです。そこで私は役割を細かく割り振り、少しずつ進んでいることを可視化しました」
このように“状況 → 行動 → 結果”の流れで話せると説得力が段違いです。
面接官が「履歴書より大事」と思っていること
- 自分の言葉で話せるか
─ 書類に書いた内容を、自然な言葉で説明できるかどうか。 - 素直さ
─ 分からない質問に「分かりません」と正直に言えるか。 - 相手とのキャッチボール
─ 一方的にしゃべるのではなく、面接官の反応を見ながら会話できるか。
これらが合否に直結しています。
面接官の視点からのアドバイス
- 履歴書は「きっかけ」であって「勝負の場」ではない
- 面接では「書いてあることを繰り返す」のではなく「裏話・背景」を語る
- 立派な言葉より「小さな体験」を具体的に話すほうが刺さる
履歴書に時間をかけるよりも、自分のエピソードを人に話してみる練習に時間を割く方がはるかに効果的です。
まとめ
面接官は、履歴書をほとんど見ていません。
私たちが知りたいのは、その人がどんな考え方を持ち、どんな行動をしてきたか。
だからこそ、あなたに必要なのは「完璧な履歴書」ではなく、自分の言葉で自分を語る力です。
履歴書は、あなたという人を知るための“入口”にすぎません。
本当に評価されるのは、入口を通った先にある「あなた自身の声と表情」なのです。