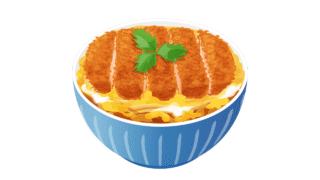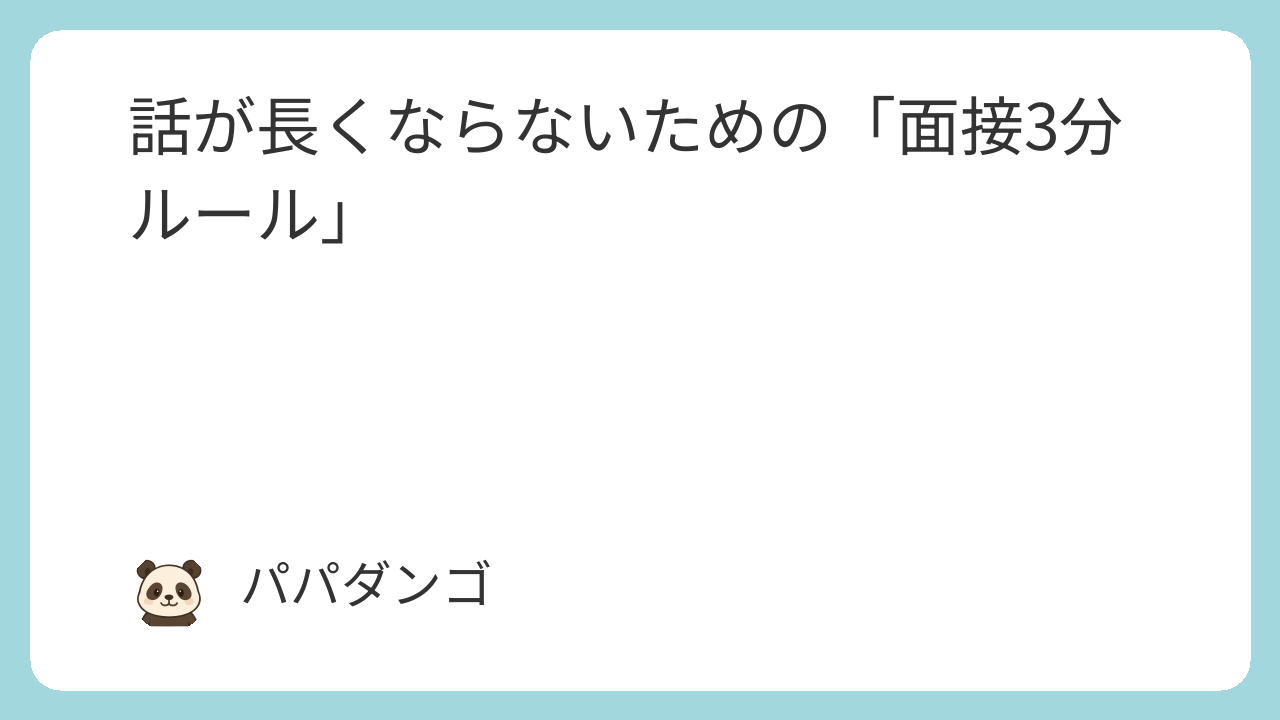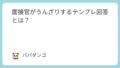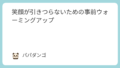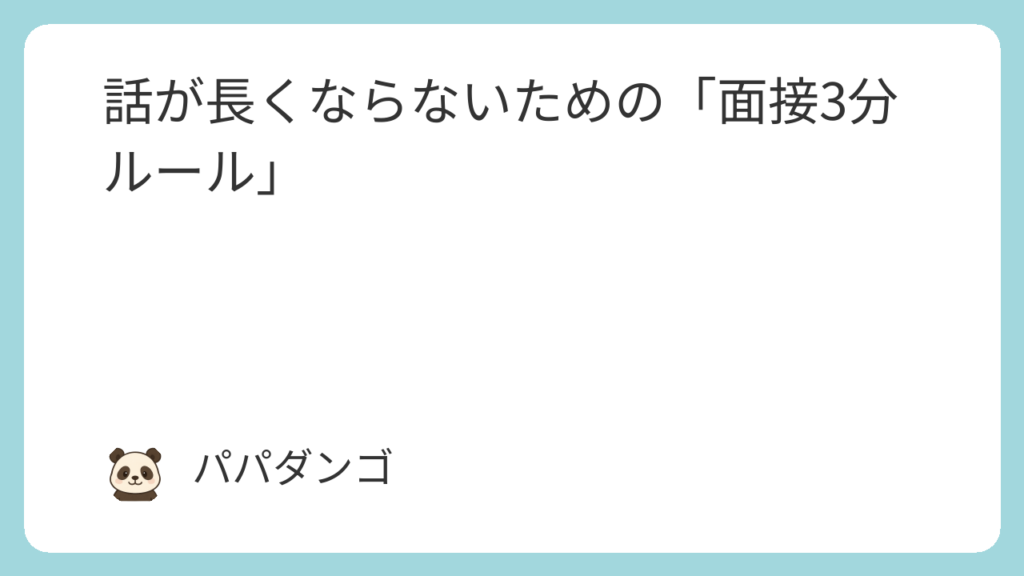
面接のとき、「自己PRをお願いします」と言われて、つい5分も6分も話してしまったことはありませんか?
その場では「全部伝えたぞ!」と満足しても、面接官の顔が微妙だったり、最後の方はメモも取っていなかったり…なんてこともあります。
実は面接官の集中力は、長くても3分が限界。それ以上話すと、情報は右から左に抜けていき、印象もぼやけてしまいます。
そこで今回は、現役の面接官として私が推奨している「面接3分ルール」を紹介します。
このルールを使えば、面接での回答が「簡潔かつ印象的」にまとまります。
そもそも、なぜ3分なのか?
- 人間の集中力は短い
脳科学的にも、人が集中して話を聞けるのは2〜3分程度と言われています。
特に面接では、面接官は一日に何人も見るため、聞く側の集中力はさらに短くなります。 - 情報は多いほど記憶に残らない
10個のエピソードを話すより、1〜2個の強いエピソードを深掘りした方が覚えてもらえます。 - 会話のキャッチボールがしやすい
3分以内で終えると、面接官が質問しやすくなります。双方向のやり取りが増えると、好印象につながります。
面接3分ルールの基本構造
話を3分にまとめるためには、PREP法を使うのがおすすめです。
- P(Point):結論から話す
- R(Reason):理由を述べる
- E(Episode):具体例を出す
- P(Point):再度結論で締める
この流れで話すと、自然と3分以内に収まります。
実際の例:自己PR
NG例(6分かかるパターン)
「私は学生時代にバイトで〜、そのときこういうことがあって〜、さらにゼミでは〜、あとサークルでも〜…」
→ エピソード詰め込みすぎで焦点がぼやける。
3分ルールの例
- 【結論】「私の強みは、課題解決に粘り強く取り組む姿勢です」
- 【理由】「これは大学時代の接客アルバイトで培いました」
- 【具体例】「常連客のクレーム対応を任され…(経緯・行動・結果を簡潔に)」
- 【再結論】「この経験を活かし、御社でも課題に前向きに取り組みたいと考えています」
この流れなら、余裕を持って3分以内に収まります。
面接3分ルールを守るための3つのコツ
- ストップウォッチで練習する
本番前に必ず計ってみましょう。意外と話が長くなっていることに気づきます。 - 1つの質問に対してエピソードは1つまで
複数入れると、話が広がりすぎて収集がつかなくなります。 - 結論を先に言う癖をつける
ダラダラ説明してから結論に行くと、聞き手は途中で離脱します。
面接官の本音
正直なところ、長く話す応募者は「自己管理ができない人」「要点を絞れない人」という印象を持たれがちです。
逆に、短く端的に話せる人は「整理されていて仕事ができそう」と思われます。
特に中途採用やマネジメント職では、時間内に要点をまとめる力は必須スキル。面接は、その能力を測る場でもあります。
まとめ
- 面接では「3分ルール」が鉄則
- PREP法で組み立てると自然に3分以内に収まる
- エピソードは1つに絞る
- 練習で必ず時間を計る
面接は情報を全部出す場ではなく、面接官が「もっと聞きたい」と思うきっかけを作る場です。
3分ルールを意識すれば、短くても印象に残る回答ができます。
次の面接で、ぜひ試してみてください。